目次
― 間違ってもOKな場面設計 × 模倣 × 成功の記憶で育てる“話す自信”
「英語で話すの、なんか恥ずかしい…」
「合ってるか分からないから、話したくない…」
― それ、“英語力”じゃなく“安心できる話す場”の問題かもしれません。
👁 本記事の視点
☑ 英語で話すことに対して強い抵抗がある
☑ 恥ずかしがって声が出ない/小さい
☑ 英語の発話を避けたがる(特に他人の前で)
それ、“自信のなさ”でも“能力不足”でもなく、
「間違えても大丈夫」と感じた経験の不足かもしれません。
✨ 教育理論・心理的安全性の視点
| 理論・モデル | 支える力 |
| 情動フィルター仮説(Krashen, 1982) | 不安が高いと習得が阻害される。安心があってこそ学びは深まる |
| モデリング理論(Bandura) | 親や他者の言動を見て、自分でもできると思える |
| セルフエフィカシー理論(Bandura) | 「自分にもできそう」という感覚が行動の鍵になる |
✅ 家庭でできる!“英語を話す自信”を育てる3つのしかけ

① 「話す内容を“成功の記憶”に変えるスクリプト練習」
📍目的:自分の口から英語が出る経験 → 自信に変える
実践法:
- 毎日1フレーズだけ親と“同じやり取り”を繰り返す
例:親「How are you?」→ 子「I’m fine, thank you.」 - 成功したらすぐに笑顔・拍手でポジティブな記憶にする
- フレーズは変えずに繰り返すことで「できた!」を積む
🧠 話す力は「話せた経験」でしか育たない
② 「“英語ごっこ”で主語を変えるだけゲーム」
📍目的:自分の意見ではなく“役になりきる”と恥ずかしさが減る
実践法:
- 親子で英語の“やり取りごっこ”
例:「Hello, I’m a robot.」「Nice to meet you!」 - 主語や立場だけ変えて、同じセリフを入れ替える
- 恥ずかしがる子には「ぬいぐるみに言わせる」→安心して言える
🧠 恥ずかしさの正体は「自分のままで話す不安」→ 役になりきれば軽減できる
③ 「英語の“音声だけチャット”を親とやる」
📍目的:視線や反応を気にせず、自分のペースで話す経験を積む
実践法:
- スマホの録音機能で「おやすみEnglish」など一言メッセージを交換
- 文字なしで“音だけ”のやりとり(言えたらOK)
- 1日1フレーズでいい。できた!を音で記録する習慣に
🧠 話せた“記録”が自信を積み上げていく土台になる
⚠ よくある誤解と注意点
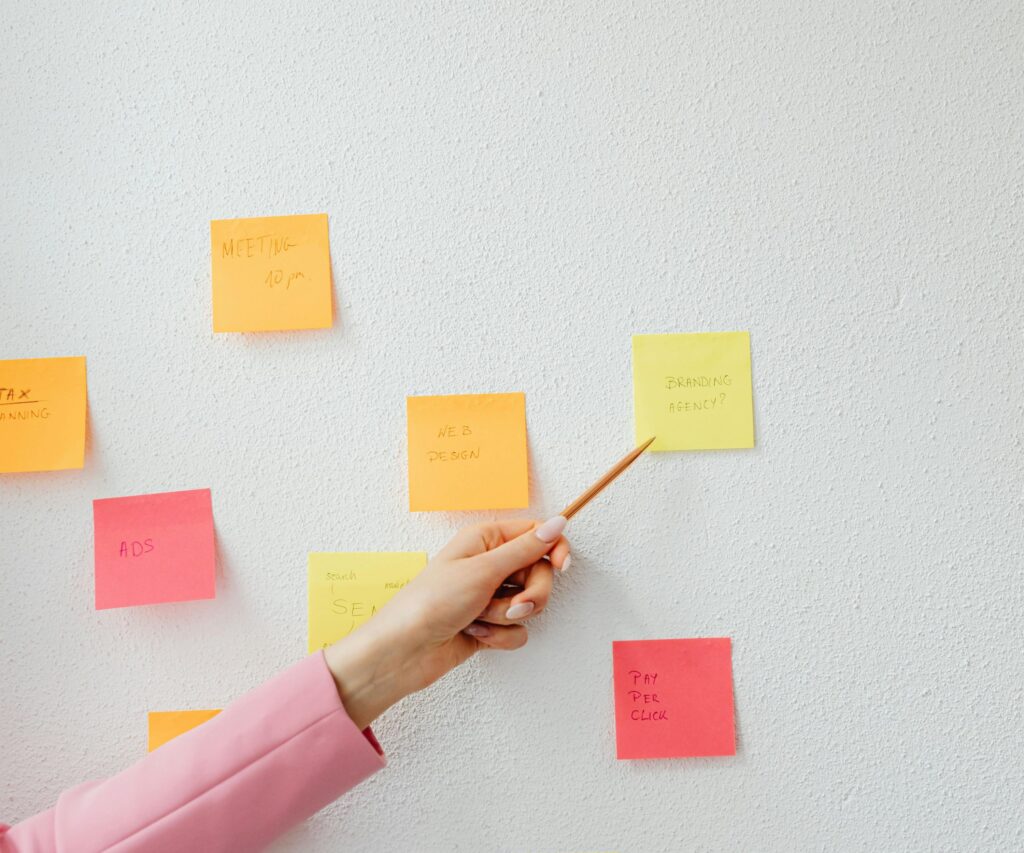
| 誤解 | 実際は… |
| 「話せない=英語力がない」 | → 話す自信と環境の問題が大きい |
| 「恥ずかしがるのは性格」 | → “大丈夫な経験”を積めば誰でも変わる |
| 「話させれば慣れる」 | → 恥ずかしさが強いと逆に“話さない回路”が強化されることも |
🧠 裏付けとなる研究・理論
- Krashen’s Affective Filter Hypothesis:「不安・緊張」が高いと習得が阻害される
- Bandura’s Modeling & Self-Efficacy Theory:自分でもできそうという信念が行動の鍵
- Vygotsky’s ZPD:大人と一緒にやることで“自分一人でもできる”へと移行する
🧩 まとめ:「英語を話すのが恥ずかしい子」は、“失敗しても安全”を知らないだけかもしれない

親ができることは:
✅ “同じフレーズ”で成功経験を積み重ねるスクリプト練習
✅ 役になりきる・ぬいぐるみに言わせるなど“自己から距離”をとる工夫
✅ 視線のない環境(音声のみなど)で小さな発話の機会を日常に入れる
話す力は、“できた体験”と“安心感”の上にしか育ちません。

