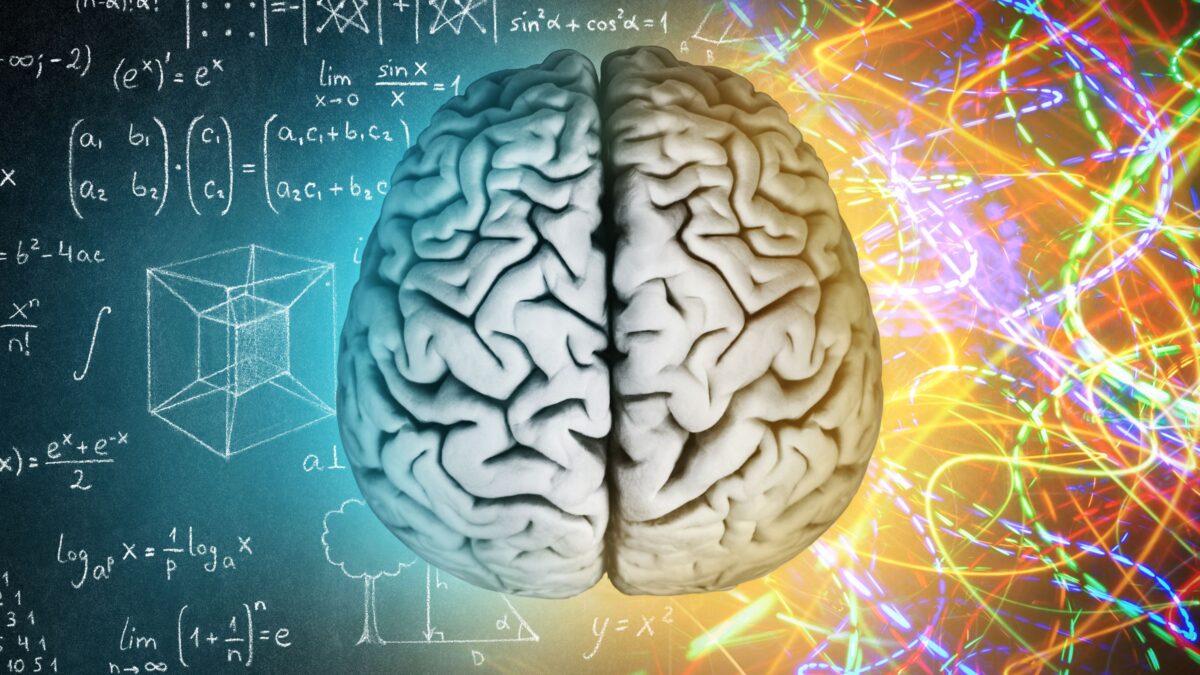目次
― 意味のつながり × 五感記憶 × 経験と関連づけで育てる“忘れない英単語”
「何回書いても英単語を覚えられない」
「テストの時だけ覚えてるけどすぐ忘れる」
― それ、“英語の言葉の森”が育っていないだけかもしれません。
👁 本記事の視点
☑ 書いても覚えられない・すぐ忘れる
☑ 覚えても“意味”とつながらない
☑ スペルと音が一致しない/丸暗記になる
それ、記憶力の問題ではなく、“意味・経験・音”との接続が不足しているからです。
言葉は“使った・見た・感じた”こととセットにすると、驚くほど定着します。
✨ 教育理論・記憶理論の視点
| 理論・モデル | 支える力 |
| 意味記憶とエピソード記憶(Tulving, 1972) | 「経験に結びついた語」は忘れにくい |
| セマンティックマッピング(Semantic Network Theory) | 意味どうしをつなげることで記憶の再生が容易になる |
| デュアルコーディング理論(Paivio, 1986) | 文字と絵や動作など、複数経路で覚えると記憶が強化される |
✅ 家庭でできる!“忘れない語彙”を育てる3つのしかけ

① 「単語を“絵・動作・経験”と一緒に覚える」
📍目的:意味記憶ではなく“感覚記憶”で覚える
実践法:
- “apple”→絵+実物+食べながら発音
- “run”→走る動作とセットで覚える
- 親が動きながら言って、子どもに“真似と発音”をさせる
🧠 単語は「文字の塊」じゃない。「動き・感覚・場面」とセットにすると忘れない
② 「“似た意味・対義語・カテゴリ”で語をつなげる」
📍目的:バラバラな単語を“ネットワーク化”して覚える
実践法:
- “hot / warm / cold / cool”など対比とグループでセット覚え
- 食べ物・動物・学校などテーマ別のミニ辞書を作る
- 単語カードに「似た言葉」や「反対の言葉」を手書きでつなげる
🧠 脳は「関係があるものほど一緒に覚える」仕組みを持っている
③ 「“使った単語”だけをまとめる“自分語彙ノート”」
📍目的:記憶するより“使って残す”を目的にする
実践法:
- その日話した単語・文章を1文だけ書く
- 絵・写真・動画と一緒に単語を“貼る・描く”など五感を活用
- 「昨日の単語で今日も1文書こうゲーム」を習慣にする
🧠 覚えるより、「使ったことがある」という経験のほうが定着する
⚠ よくある誤解と注意点

| 誤解 | 実際は… |
| 「書いて覚えるのが一番」 | → 書くだけでは“意味のネットワーク”が構築されない |
| 「1日10語覚えさせよう」 | → 単語数より“意味の深さ”と“使った経験”が大事 |
| 「忘れたのは努力不足」 | → 脳が“関連づけ”しやすい設計をしていないだけ |
🧠 裏付けとなる研究・理論
- Paivio’s Dual Coding Theory:視覚+言語を組み合わせると記憶が倍増
- Semantic Mapping (Collins & Quillian, 1969):意味どうしの“つながり”が思い出しやすさを決める
- Baddeley’s Working Memory Model:短期記憶は意味処理と視覚情報が同時に働くと強化される
🧩 まとめ:「英単語が覚えられない子」は、“関連と感覚”がセットになっていないだけかもしれない

親ができることは:
✅ 単語を絵・動作・体験と結びつけて教える
✅ 意味・カテゴリ・対義語で“ネットワーク記憶”を作る
✅ 書くより「使った・言った・貼った」語を記録する
語彙力は、記憶じゃなく“つながり”の数で決まる。