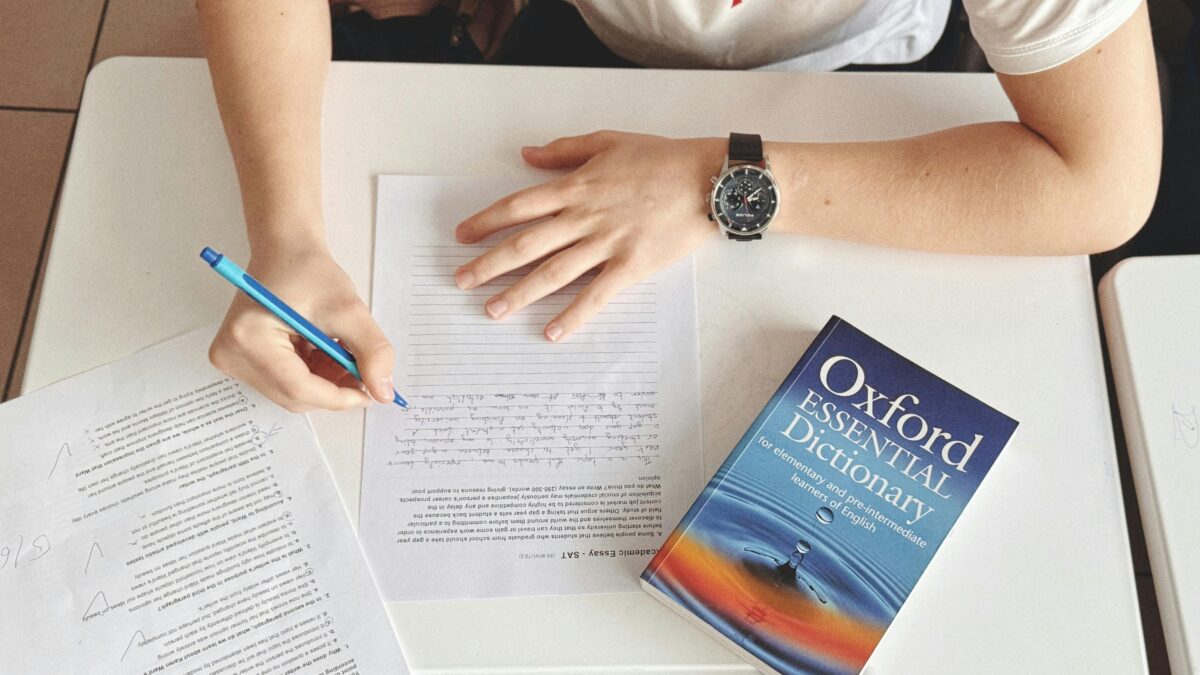目次
― 英語の並び感覚 × 型の口頭反復 × イメージと言葉の結びつきで育てる“英文組立力”
「言いたいことはあるのに、英語にできない…」
「単語は知ってるけど、文になると出てこない…」
― それ、“語順で考える脳の回路”がまだ育ってないだけかもしれません。
👁 本記事の視点
☑ 英語の単語は知っているのに、文章にできない
☑ SVO(主語・動詞・目的語)の並びがうまく使えない
☑ 日本語で考えてから英語に直すクセがある
これ、語順に沿って“思考から言葉を並べる訓練”が足りないだけかもしれません。
大切なのは、「言いたいこと」→「英語の並び」で考える回路を作ること。
✨ 教育理論・習得アプローチの視点
| 理論・アプローチ | 支える力 |
| オーラルパターンプラクティス | 文型を「音と順」で身につける反復法 |
| 生成文法(Chomsky) | 言語は“ルールの再利用”で無限に文を作れる |
| ビジュアルセンテンスマッピング | 絵・アイコンで「語順と意味」を視覚的に一致させる方法 |
✅ 家庭でできる!“文を組み立てる力”を育てる3つのしかけ
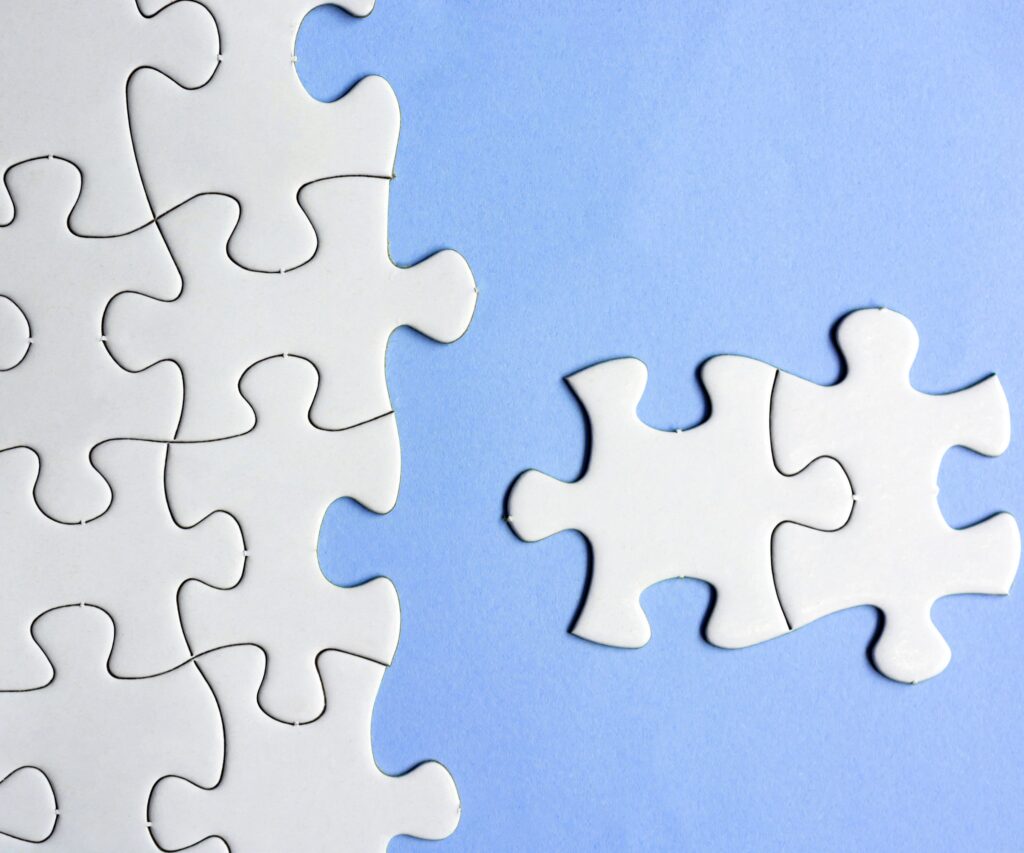
① 「“言える型”を3つだけ決めて、主語・目的語だけを変えて遊ぶ」
📍目的:SVOパターンを身体に入れる
実践法:
- 例:「I like ○○」「She plays ○○」「We go to ○○」
- 主語と目的語をいろんなバリエーションで入れ替えて毎日遊ぶ
- 「今日は“do you like〜?”だけで遊ぼう!」でもOK
🧠 英語は“並び”が全て。型を毎日ちょっとずつ変えると「文」が自然に出てくるようになる
② 「絵カードで“並び順パズル”を作る」
📍目的:目で見て語順を感覚でつかむ
実践法:
- 絵や写真カード(例:boy / eat / apple)を使って、「どう並べると意味が通るか」遊び
- 親がバラバラにして「どの順が正しいと思う?」と問いかける
- 順番が合ったら、「That’s right! Say it!」で発話につなげる
🧠 正しい並び=意味が伝わるという感覚を“視覚+意味”で定着
③ 「“日本語→英語1文変換”の口頭ゲームを日常に」
📍目的:日本語で考えてから翻訳するクセを減らす
実践法:
- 親が「今日、何食べた?」→「I ate curry.」など1文返し
- 「電車に乗るって英語で言える?」→「I ride a train.」
- 答えがすぐ出なくても「一緒に考えよう」で安心感を保つ
🧠 単語の知識ではなく「語順で考える」経験が反射的に文を出す力になる
⚠ よくある誤解と注意点

| 誤解 | 実際は… |
| 「単語さえ知っていれば話せる」 | → 文の並び方が身についていないと使えない |
| 「文法を教えれば自分で組み立てられる」 | → 理解より反復と体得が先 |
| 「英作が苦手なのは表現力の問題」 | → 多くは“語順処理の未熟さ”による出力障壁 |
🧠 裏付けとなる研究・理論
- Krashen’s Input→Output理論:理解できるインプットのあとに、小さなアウトプットで表現力が伸びる
- Nation (2009):語順と構文は「パターンの再利用」が自然習得の鍵
- Willis (1996):タスク中心言語学習(TBLT)では“使える構文”が定着の主役になる
🧩 まとめ:「英語で文が作れない子」は、“語順で考える経験”が圧倒的に足りていないだけかもしれない

親ができることは:
✅ 使える型を3つだけに絞り、主語・動詞・目的語を入れ替えて遊ぶ
✅ 語順パズル・カードなど“並びの感覚”を視覚で育てる
✅ 日常会話の中で「1文英訳ゲーム」を毎日1回だけやってみる
“語順の感覚”は、知識ではなく“使った回数”でしか育たない。