目次
― 音のまとまり/意味づけ/リズムと繰り返しで育てる“英語耳”
「聞き流してるのに聞き取れない」
「単語は知ってるのに聞こえない」
― それ、“音の意味化”が起きてないだけかもしれません。
👁 本記事の視点
☑ 英語のリスニング音声が「音のかたまり」にしか聞こえない
☑ 単語は知ってるのに、聞いたときに意味がつながらない
☑ 聞き流し教材を続けても、聞こえた実感がわかない
それ、耳が悪いのでも集中してないのでもなく、
「音と意味のリンク」が脳内でできていないからです。
✨ 教育理論・音声習得アプローチ
| 理論・アプローチ | 支える力 |
| 音韻知覚(Phonemic Awareness) | 英語の“音のかたまり”を区切って認識する力 |
| 第二言語の意味処理(Semantic Mapping) | 聞いた音を“瞬時に意味づける”脳内回路が必要 |
| リズムとチャンク学習(Chunking) | 音を“かたまり”で覚えると、脳に負荷が少なくなる |
✅ 家庭でできる!“英語耳”を育てる3つのしかけ

① 「意味の分かるフレーズを“何度も、リズムで”聞く」
📍目的:音=意味として“脳が認識する瞬間”をつくる
実践法:
- “Let’s go!” “Here you are.” “I got it!”など意味付きチャンクを使う
- 日常会話で“1日1チャンク”を耳に入れる習慣をつくる
- リズムに乗せて(例:「Clap! Clap! I got it!」)で、音と意味の同時学習
🧠 音が“意味のあるもの”とリンクしてはじめて「聞こえた」になる
② 「“聞こえた言葉を口に出す”を毎回セットに」
📍目的:聞いた音を“自分の中で再現”して定着させる
実践法:
- 絵本や英語動画のあとに「真似っこタイム」→聞こえた音を復唱
- “音読”よりも“復唱(リピート)”を重視する
- 親が1回、子が1回の交互シャドーイングでもOK
🧠 「聞く→出す」プロセスがあると、音は“再処理”されて定着する
③ 「“聞こえた音の中に単語を見つける”遊びで、脳を英語音に慣らす」
📍目的:英語音の“変化”に慣れて「意味が浮かぶ耳」を育てる
実践法:
- “I’m gonna go.” など音がつながるフレーズを探す
- 「今、どの単語が聞こえた?」クイズ形式で遊ぶ
- 「ウォナゴー?→Want to go か!」という“気づき”を積む
🧠 英語の音変化(リンキング・短縮)を“楽しむ感覚”が、聞こえの基盤になる
📍実践法
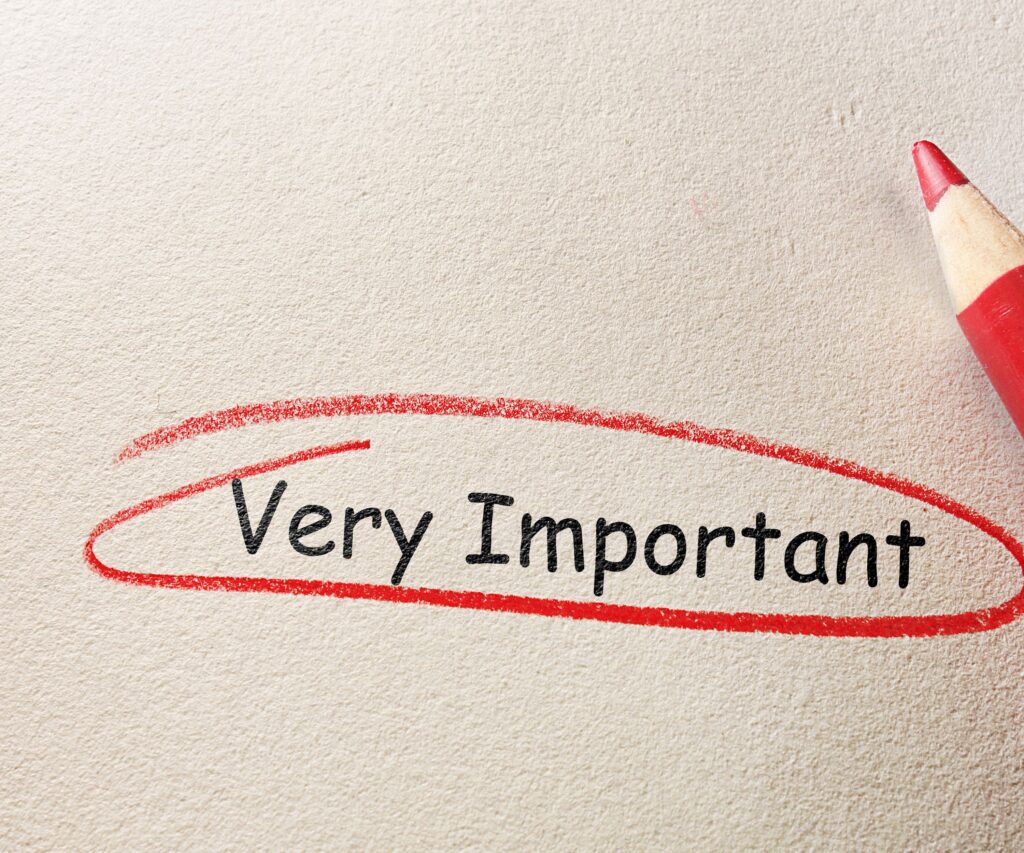
| ❌ 誤解 | ✅ 実際は… | 🏡 家庭でできること |
|---|---|---|
| 「聞き流していれば耳が慣れる」(毎日BGMのように英語を流してるのに効果がない…) | → 意味のない音は、脳にとってはただの雑音として処理される | 🔸「知ってるフレーズ」や「一緒に動ける歌」など、意味づけされた音声だけを短時間で流す🔸例:毎朝“Let’s get dressed!”の歌を一緒に歌う→服を着る→言葉と行動がリンク! |
| 「発音ができない=リスニングもできない」(言えない音は聞こえない、と思って焦って発音練習から始めてしまう) | → 本来は逆。まず「意味のある音をたくさん聞いて慣れる」ことが先 | 🔸いきなり発音練習より、「親が英語で話すのをジェスチャー付きでたくさん聞かせる」🔸例:「Here you are.(はいどうぞ)」を毎日おやつの時に→“意味ある音”としてインプットされていく |
| 「聞こえない=集中力がない」(よそ見してるから聞いてない/注意散漫なのかも?) | → 実際は「音と意味がつながってないから記憶に残らない」だけ | 🔸集中させるより、「聞こえた音をすぐに“まねする時間”をセットにする」方が効果的🔸例:親「I got it!」→ 子どもがすぐにまねする→“音→意味→再現”の脳内ループが生まれる |
🔑 ワンポイントまとめ:
英語の音は、“意味をともなった体験”の中で初めて聞こえるようになる。
ただ聞かせるのではなく、「どんな状況で、何の意味でその音が使われているか」をセットにして届けましょう。
🧠 裏付けとなる研究・理論
- Field (2008):「リスニング困難は音の知覚でなく、意味処理の遅延に起因」
- Nation & Newton (2009):「“理解可能な音のかたまり”がなければ脳は学習として処理しない」
- TPR・シャドーイング・チャンク学習の有効性は第二言語習得で実証多数
🧩 まとめ:「英語が聞き取れない子」は、“音の意味化”を経験していないだけかもしれない
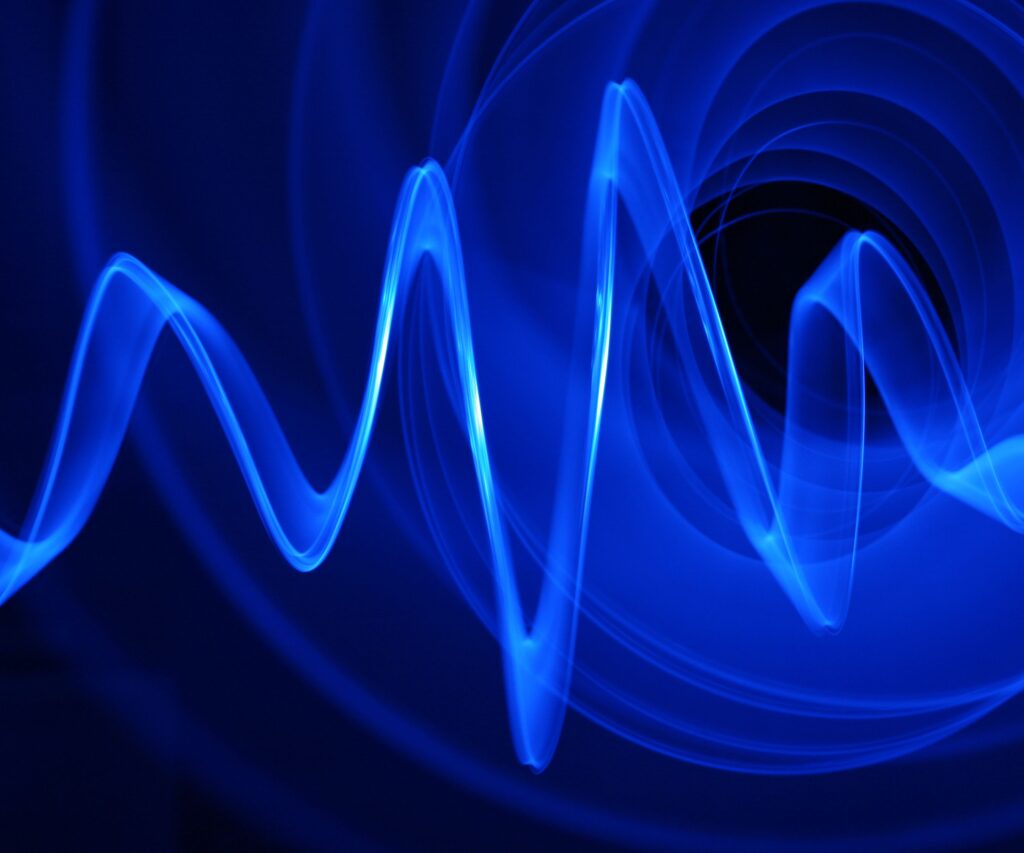
親ができることは:
✅ 意味付きチャンクを日常に入れ、音=意味のリンクを育てる
✅ 聞いたあとに声に出すことで“脳の再処理”を促す
✅ 音のかたまりで英語を捉える遊びを取り入れる
聞こえる耳は、“意味づけされた音”からしか育ちません。

