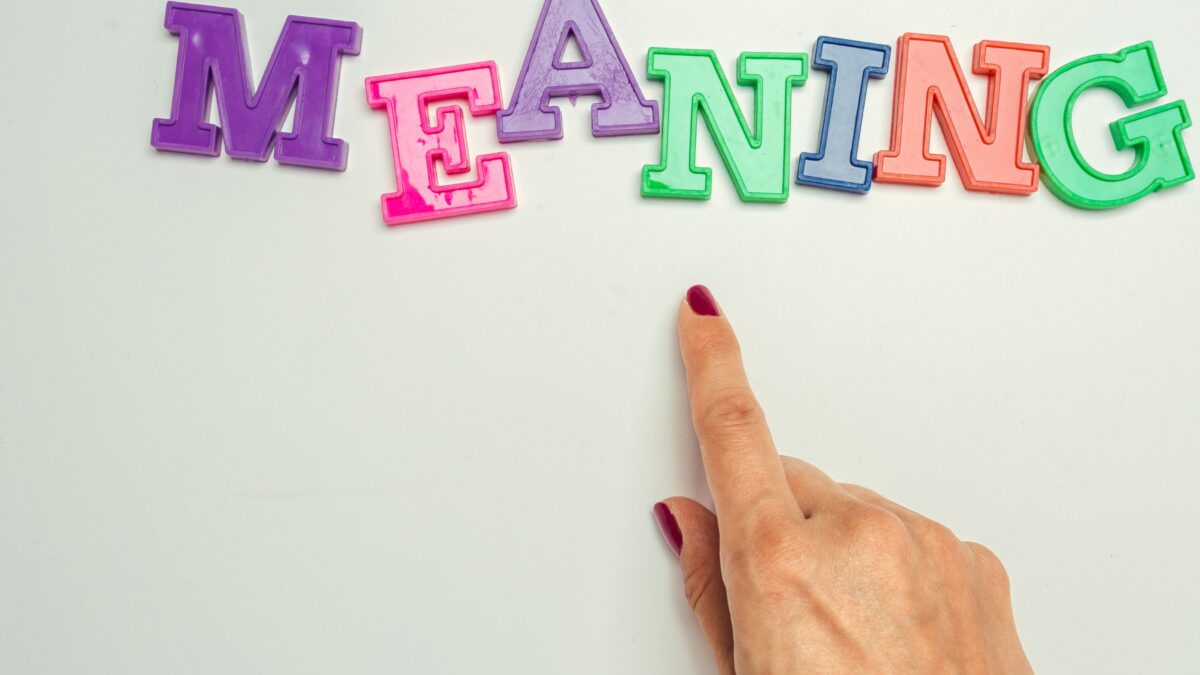― プログラミングで“飽きっぽい”のは、課題の出し方と“目的の断絶”に理由がある
🧠 本記事が基づく教育法とその要素
| 教育法 | 活用された視点・キーワード |
| 📚 PBL(プロジェクト型学習) | 実社会との接点、探究活動の意味、ゴール設計 |
| 🧠 ハビット・オブ・マインド | 粘り強さの育て方、目的との再接続 |
| 📖 コンストラクティヴィズム | 「今やっていることに意味を持たせる」自己構築的学習 |
| 🌱 モンテッソーリ教育 | 子どもの“やりたいこと”と“反復”のズレを観察する姿勢 |
🧩 こんな症状ありませんか?
- 途中まで熱中してたのに、急に飽きてやめる
- 何度も似たようなことをさせると「もうやったじゃん」と拒否
- ScratchやPythonで基礎的なことはできるけど、“応用に移らない”
これは「集中力がない」からではなく、“何のためにやっているのかが途切れた”状態かもしれません。
🔍 「同じことの繰り返し」が意味を持たなくなった瞬間、やる気は消える

PBLでは、学びの反復は“必要な繰り返し”であるべきとされます。
つまり、「やりたいゴール」のために必要だからやる、という文脈。
ところが、「とりあえず練習」「慣れるまで反復」のような目的の希薄な繰り返しは、
意味が見えず「ムダな作業」として切り捨てられやすいのです。
📚 PBLの視点:「練習」ではなく「目的達成のための準備」として繰り返す
例:
| 退屈な課題 | 意味のある課題 |
| 5回連続でif文を書く | キャラの「分岐する運命」を作るための分岐条件を試す |
→“なぜやるか”が見えれば、繰り返しは“必要な手段”になる
🧠 ハビット・オブ・マインドの視点:「飽きた」と感じるのは、“価値と接続していない”サイン
子どもの中で「これは意味ある」と納得できていないと、継続は続かない
→ 逆に“価値を再発見する問い”があれば、もう一度繰り返せる
📖 コンストラクティヴィズムの視点:「ただの練習」ではなく「自己目的化」させる
学びは「これは自分に必要だ」と子どもが意味づけして初めて深くなる
✅ 家庭でできる!「飽きやすい子」に効く“意味の再接続”3ステップ

① 【意味を聞く】
📌 PBL×ハビット視点:「この練習って何の役に立つ?」を一緒に考える
🎯 目的:
「ただやらされてる練習」→「自分にとって必要なもの」へと変換する
🏡 会話例:
👧「また同じやつやるの?if文、もう知ってるし」
👨「うん、知ってるよね。でもさ、“このif文”って、前に作ったシューティングゲームの“敵の動き”に使えそうじゃない?」
👧「あー、ライフが0になったときのゲームオーバーのとこ?」
👨「そうそう。そこ、自動で止まるようにするには条件分岐が必要だったでしょ?」
→ 「練習=役に立つ技術」だと自分で納得すると、再び集中しやすくなります。
② 【応用の場面を提案】
📌 コンストラクティヴィズム視点:「知識の転用」で実感を深める
🎯 目的:
「やったことを別の形で活かす体験」=“繰り返し”の意味づけ
🏡 実践例:
👨「この前“ジャンプするキャラ”作ったよね。今度は、“ジャンプするけど空中で攻撃もする”ゲームにできないかな?」
👦「できるかも!if文で“スペースキー押してる”って条件つければ…」
👨「それだね!じゃあさ、前のコードちょっと使い回して、新しい場面作ってみようか」
→ 子どもが「前の知識が活きる!」と感じた瞬間、“反復の目的”が自然に立ち上がります。
③ 【ループ設計】
📌 モンテッソーリ的反復の意図化:「わかる→使う→工夫する」の循環
🎯 目的:
「練習→応用→編集→応用」の流れを子どもが自分で見通せるようにする
🏡 実践例(ScratchやPythonで):
- 🔁 STEP1(わかる):「まずは基本のif文で、プレイヤーが敵に当たったらゲームオーバーにする」
- 🧩 STEP2(使う):「作ったそのコードを、自分の“迷路ゲーム”にも組み込んでみる」
- ✏️ STEP3(工夫する):「ゲームオーバー画面に“リスタートボタン”を追加したい!どうやったらできる?」
→ 「コードを書く意味が変わる」=ただの反復が、“自分の発想を実現する道具”に昇格します。
💥 NG対応例【具体的に】
| ❌ 大人の声かけ | 🙅 背景意図 | 🧒 子の内心反応 |
|---|---|---|
| 「同じの繰り返さないと覚えないよ」 | スキルの定着を重視 | 「またか…意味わかんない…」→集中力低下 |
| 「我慢してやれば上手くなるから」 | 忍耐の価値を教えたい | 「やらされてる感じしかない」→投げ出す |
| 「まだ甘い!だから上達しないんだ」 | 厳しさでモチベーションを維持したい | 「怒られるからやる」→内発的動機が消える |
✨まとめ:「飽きっぽい」のは、“学びの価値との接続が切れた”サインかもしれない

✅ 「これって何のため?」を毎回問い直す
✅ 使う場面・展開する場面を一緒に描く
✅ 反復が“創造の一部”になれば、子どもは自然に続ける