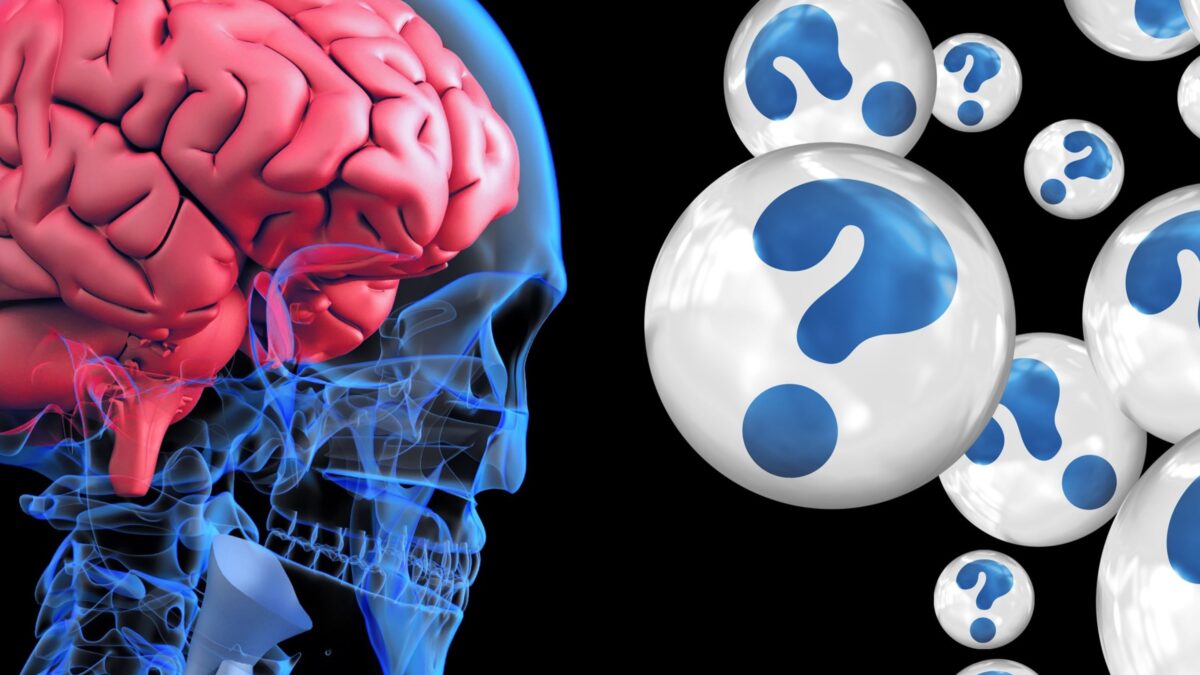目次
― 「すぐに手を動かさない子」に見られる“見えない思考”の価値と育て方
🧩 こんな子、見たことありませんか?
- プログラミング中、動きがほぼ止まっている
- でも急に正確なコードを打ち始めて一気に完成
- 「なに考えてるの?」と聞くと「今、どうなるか考えてた」
多くの大人はこう言ってしまいがちです:
「止まってないで、まず試してみようよ!」
でも実はその“止まってる時間”こそ、
「仮説思考」「予測処理」など、実は高度な思考活動が行われている時間かもしれません。
🧠 子どもは“頭の中でコードを動かしている”ことがある

ブレイン・ベースド・ラーニングの視点では、
実行機能(前頭前野)を使って「●→▲→■」のような一連の動作を、実際に動かす前に脳内で“リハーサル”していると考えられます。
この内的リハーサル(mental rehearsal)は以下のような力と関係しています:
- ワーキングメモリ(仮の手順を頭に留めておく力)
- 見通し力(手順全体の完成イメージを描く)
- 認知的予測(結果を見積もる)
つまり、動いていない=止まっているではないのです。
🏠 モンテッソーリ教育の視点:
子どもの行動を「観察」することが出発点。
「今この子は何をしようとしているのか?」という“内的動機”を信じる。
この視点に立てば、
じっとしている子も「自分で選んで思考している」=大切な活動の最中だと捉えられます。
📖 コンストラクティヴィズムの視点:
子どもは、自らの経験から意味を作り、知識を“構築”していく。
行動より「内的経験」が重要な場面もある。
✅ 家庭でできる“シミュレーション脳”のサポート法

① 【声かけ】「いま、頭の中で何か試してる?」
📌 子どもの“内なる活動”に信頼を置くモンテッソーリ的関わり
- 「止まってるけど、考えてるの?」ではなく、
「どうなるか頭の中で想像してるのかな?」と寄り添い型の問いを
② 【関わり方】「すぐに動かさない時間もOK」と周囲が理解する
📌 ブレイン・ベースド・ラーニング × ハビット・オブ・マインドの視点
- ワーキングメモリが強い子は、“静かな思考”で準備をする
- その時間を尊重すると、子どもは「自分は考えるタイプなんだ」と内省が育つ
③ 【習慣化】「想像 → 実行 → ふり返り」をルーチンにする
📌 コンストラクティヴィズムに基づく「学びの自己構築」
- 「どう動くと思った?」→「結果はどうだった?」→「次はどう変える?」の流れで
“自分の思考のモデル”を理解していく
🔁 こんな誤解に注意
| よくある誤解 | 実際は… |
| 「じっとしてる=サボってる?」 | → 脳内ではシミュレーション処理中かも |
| 「手を動かしてこそ学び」 | → 学びには内的処理の段階も不可欠 |
| 「試さなきゃわからない」 | → 予測→仮説→確認の順序を大切にする子もいる |
✨まとめ:「止まっているように見える子」は、“動いていない”のではなく、“頭で動かしている”のかもしれない。
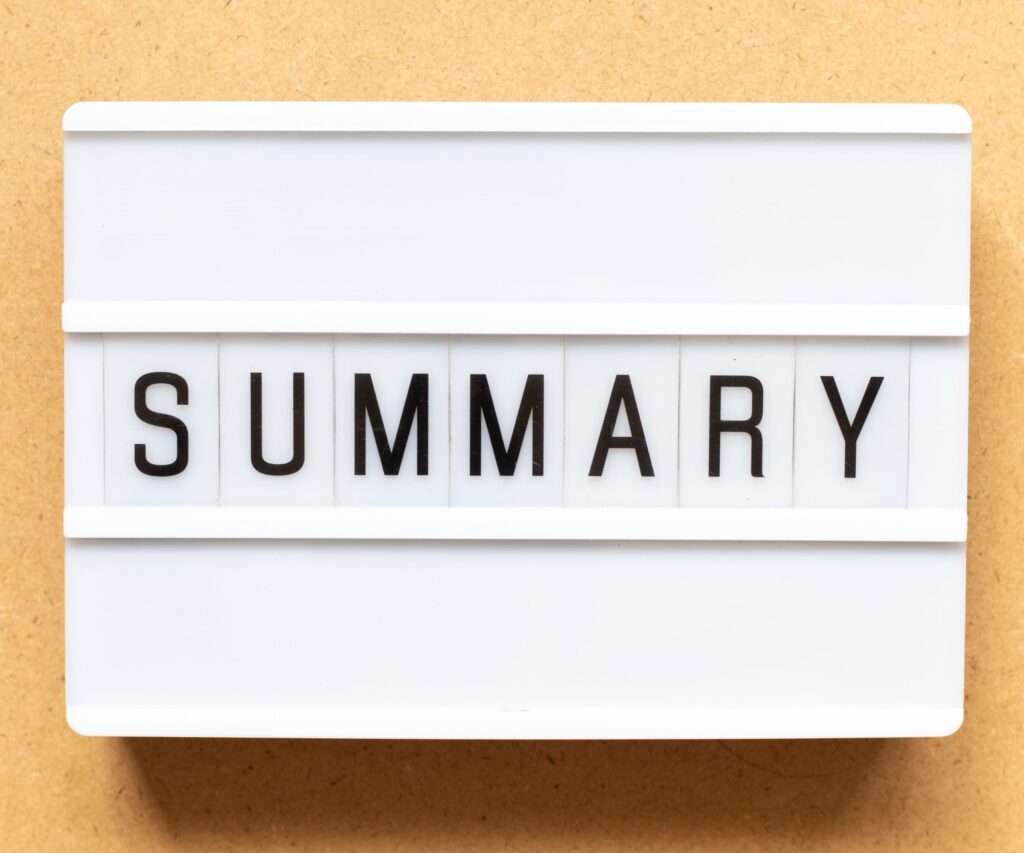
「もっと動いて!」よりも
「どんなふうに動くと思った?」という内的プロセスへの問いかけで、
子どもの見えない思考と自信は深く育ちます。