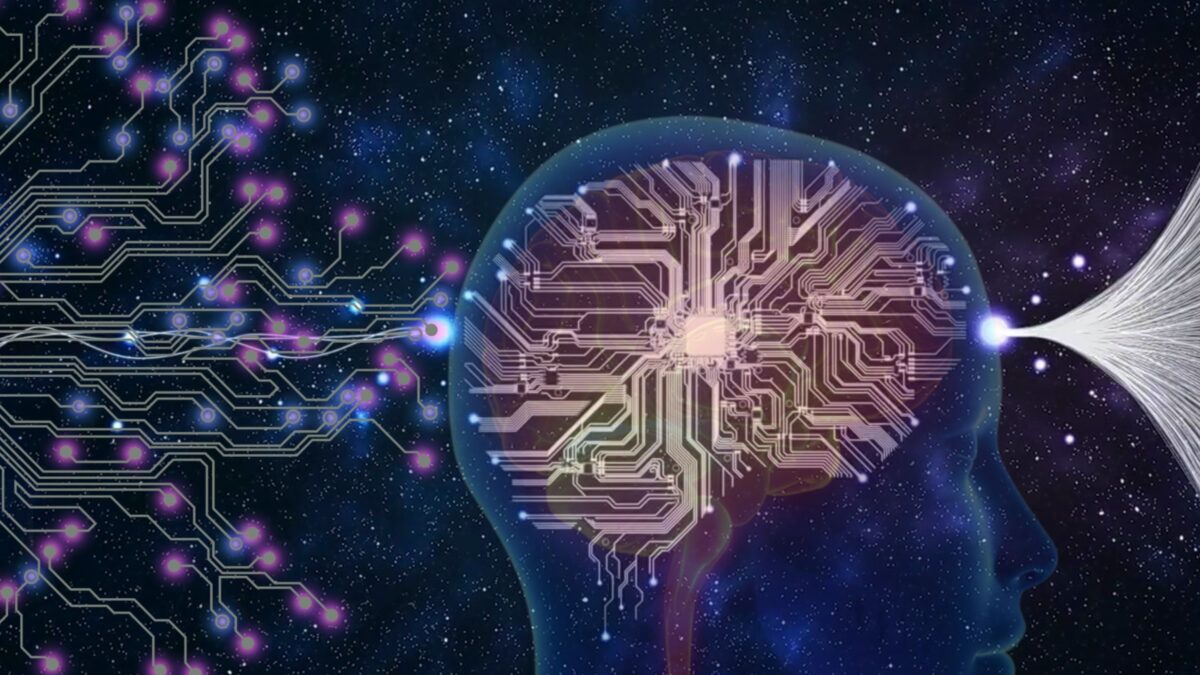― 「速さ」より「順番の見通し」が鍵
🧠 本記事が基づく教育法と要素
| 教育法 | 活用された視点・キーワード |
| 🧠 ブレイン・ベースド・ラーニング | ワーキングメモリ/認知負荷/脳の情報処理の順序性 |
| 🌱 モンテッソーリ教育 | 手順を“視覚化・具体化”して学ぶ |
| 📖 コンストラクティヴィズム | 処理の意味・順序を自分で構築する経験 |
| 🌀 シュタイナー教育 | リズムやテンポ感覚による計算構造の習得 |
🧩こんな症状ありませんか?
- 単純な計算でもとにかく時間がかかる
- 「筆算」や「繰り上がり」が混乱しやすい
- 頭で考えてる時間が長くて、手が止まりがち
→これは能力が低いわけではなく、「計算の処理順序を頭の中で整理する力」が未発達なだけかもしれません。
🧠 ブレイン・ベースドの視点:
ワーキングメモリが弱い子は、「一時的に複数の情報を保持して操作する」ことが苦手
- 繰り上がり・繰り下がり・複数ステップの処理に時間がかかるのは、「遅い」のではなく「まだ脳が整理中」
🌱 モンテッソーリの視点:
見える手順・触れる操作で、「やることの順番」を明確にする
- 筆算の処理順を、視覚や操作でサポートして“順序の型”をつくる
🌀 シュタイナー教育の視点:
リズム・テンポ・繰り返しで「処理の型」を身体に落とし込む
- 計算は“音”や“リズム”で教えると定着しやすくなる子も多い
✅ 家庭でできる!「処理順の回路」を育てる3ステップ

①【「順番シート」で手順を見える化】
📌 子どもは「どこからどう進めるか」が“頭の中で整理されてない”だけかもしれません
🧠 ポイント:手順を「思い出す」前に、「目で追える」ようにするだけで混乱が激減
🏡 家庭での使い方:
- 「足し算の手順表」や「筆算のステップカード」を作って机の横に貼る
- 一つずつ終わるたびに、シールや〇をつけて進行感を出す
🧒 例:「2桁のたし算」の順番カード
- 右の数字(一の位)を見る
- 上と下を足す(7+6)
- くり上がりがあれば“1”を十の位に書く
- 左の数字(十の位)に“1”も足してもう一度計算
👩「どこから始めるか分かると安心するよね」
👨「1個ずつチェックしていこう!“はい、1番終わり!”」
📌 ワザ:
- 手順表は【1枚にまとめず】、1ステップ=1カードにして順番に並べると、より“順を追う”感覚が育ちます
- 「できたら裏返す」「光るペンでマークする」など、視覚的にも進行を実感させましょう
②【「声に出す計算リズム」でテンポ感覚をつける】
📌 “処理スピード”ではなく、“処理のリズム”がまだ身についてないだけ
🧠 ポイント:テンポのある音やリズムが、脳内処理の“ガイド”になる
🏡 家庭での取り組み例:
- 👩「九九ラップしようか! ににんがしっ! さんにがろくっ!」
- 👨「4+3=7! 5+2=7! 6+1=7!」(手を叩きながら)
🎵 応用例:
- トントン手拍子+かけ算の暗唱
- スキップしながら「足す数リズムゲーム」
- 「計算ソング」や「九九体操」など、音に合わせて動きながら
🧒「にしがはちっ! よんごじゅう! これはリズムで覚えた〜!」
📌 ワザ:
- テンポは子どもに合わせてOK。「遅めでリズムを安定させる」が第一歩
- リズムに乗れることで、“自分でスムーズに進められる”感覚が生まれます
③【「1問を3回繰り返す」=処理回路の強化】
📌 計算が“身につく”のは、できた後に「何度も使う」から
🧠 ポイント:1問で3回トライするだけで、「やり方」が“記憶”から“処理ルート”へ
🏡 取り組み例:
🗓【月曜】
👩「今日のチャレンジ問題ね。47+38。時間計ってやってみよう!」
🗓【水曜】
👨「前やったこの問題、またやってみよっか。今日はどうなるかな?」
🗓【日曜】
👩「同じ問題、1週間たったけど覚えてる?おさらいしてみよう!」
🧒「あ、これ前やったやつ!今はスラスラできた!」
📌 ワザ:
- 「1問3回チャレンジシート」を使うと記録しやすい(時間・できた感・つまずき)
- 解くたびに色ペンを変える、タイムを測って記録するなど“見える進化”を演出
💥 NG対応例とその裏で起きていること
| ❌ 大人の声かけ | 🧒 子どもの反応 | ❌ NGシーン |
|---|---|---|
| 「もっと早くして!」 | 「焦るとミスる…」→不安で手が止まる | 🧑「まだその問題やってるの?」 |
| 「集中しなさい!」 | 「何をどうすればいいか分かってない…」→固まる | 👩「次の問題いってよ!」 |
| 「これくらいパッとできるでしょ」 | 「比べられてる感じがする」→自信喪失 | 👨「○○ちゃんはもっと速いよ?」 |
🧭 改善のヒント:
- 「早さ」を求めるより「順番が分かる安心感」を与える
- 「できた手順」や「言えたリズム」に〇をつけて、“自分でも進められた感覚”を残す
- 回答の正確さよりも、「やり方を思い出せたこと」「手順を踏めたこと」を褒める
✨まとめ:「計算が遅い子」は、“遅い”のではなく、“順番の回路”が育っていないだけ

✅ 「計算が遅い子」は、“遅い”のではなく“処理順の回路”が未発達なだけ
✅ 見える・言える・繰り返す、3つの支援で“迷いのない流れ”がつくられる
✅ スピードより「考えやすい順序」があると、自然と速く、正確になっていく