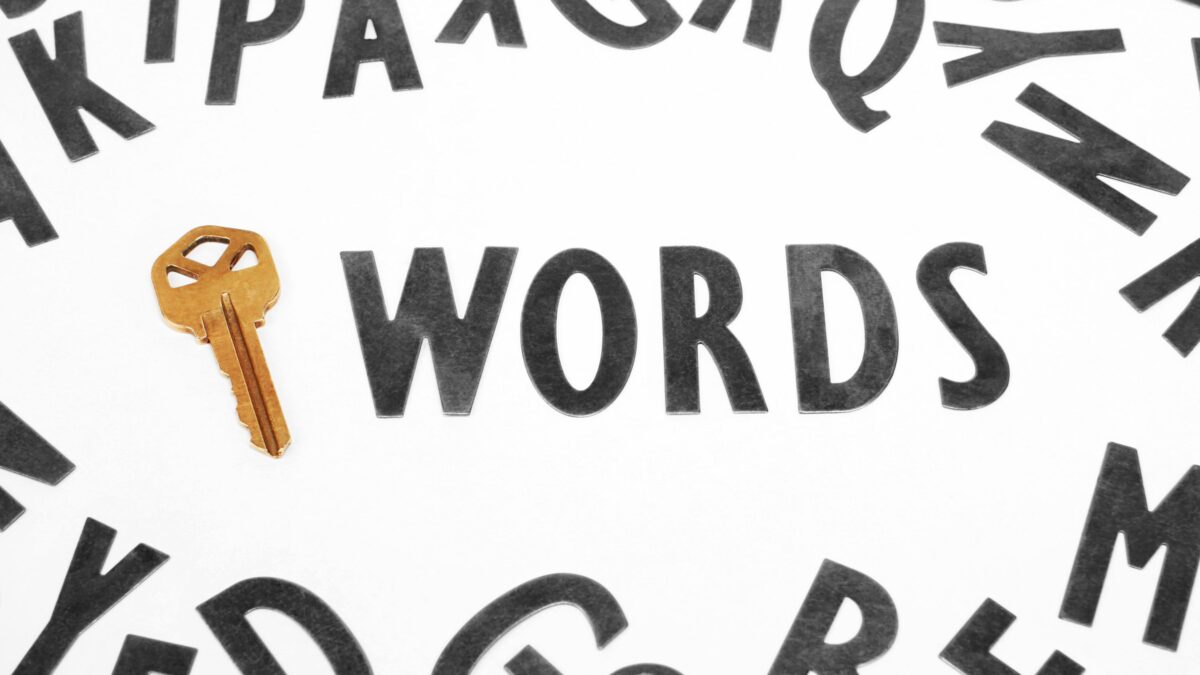― 「わかる」を「伝えられる」に変える数学の言語力育成法
🧠 本記事が基づく教育法と要素
| 教育法 | 活用された視点・キーワード |
| 📖 コンストラクティヴィズム | 学習内容の再構築・言語化による深い理解 |
| 🧠 ブレイン・ベースド・ラーニング | 表出活動(アウトプット)で記憶と定着が強化 |
| 🌱 モンテッソーリ教育 | 自分の学びを言葉で整理する「内的対話」 |
| 🌀 シュタイナー教育 | 思考と感情の結びつき・語りを重視する学習スタイル |
🧩こんな症状ありませんか?
- 「どうやって解いたの?」と聞くと「えーと……わかんない」
- 正解してるのに、説明できない・言葉が出ない
- 書いてある内容を“自分の言葉に言い換える”のが苦手
→これは理解力の問題ではなく、「言語による整理」の回数が少ないだけかもしれません。
🧠 ブレイン・ベースドの視点:
脳は「インプット→アウトプット」の流れで情報を整理・定着させる
- 解いた直後に説明できないのは、“脳内整理”が未完了な状態
- 言葉にすることで、理解の輪郭がはじめて明確になる
📖 コンストラクティヴィズムの視点:
人は「説明する」ことで学びを自分のものとして再構築する
- 「誰かに話す」「説明を考える」こと自体が深い学びになる
- 答えが出たあとにこそ、真の学びのチャンスがある
🌱 モンテッソーリの視点:
子ども自身が「どう学んだか」「どうわかったか」を言葉で内省することを重視
✅ 家庭でできる!「数学の言語化力」を育てる3ステップ

①【「どう思ったのか」を先に聞く】
📌 子どもが“考え始めた地点”に注目することで、思考の可視化がスタートする
🧠 ポイント:答えより「どこから入ったか」「何に気づいたか」に注目
→ 自分の中の思考を言葉にする土台を育てる
🏡 家庭での声かけ例:
👩「あ、正解できたね!どこからやろうって思ったの?」
👨「この問題見たとき、最初に気になったとこどこだった?」
👩「ひらめいたのって、図を見たから?計算してたとき?」
🧒「ここの数字が同じだから、そこからやってみた」
🧒「前に似た問題があって、それを思い出したから…」
📌 ワザ:
- 正解・不正解より「思考のルート探しゲーム」だと思って聞く
- 結論が出ていなくても「なるほど、そう考えたのか」が最高のフィードバック
②【「相手役」になってもらう】〜解き方を親に教える〜
📌 “教える=理解の完成”という原則を、家庭でも使う
🧠 ポイント:説明しながら、子ども自身が思考の流れを整理する
→ アウトプットを通して記憶の定着と理解の深まりが起きる
🏡 取り組み方:
- 子どもが問題を解いたあと
- 親が「ねえ、それどうやってやったの?教えて〜」と“初心者役”に
- 子どもが説明しながら、時々詰まったら「それって、何のため?」とナビゲート
👨「ここで割り算したのって、なぜだっけ?」
👩「この“□”ってどういう意味だったの?そこから考えたの?」
🧒「……うーん、あ、面積を先に出したかったんだ」
📌 ワザ:
- 親は“あえてわからないふり”をするのがコツ!
- 言い直しや詰まりもOK。むしろ「言葉を探す経験」が大事
③【「別の言い方ある?」と言い換えゲーム】
📌 抽象語(数学語)→具体語(生活語)への変換で、概念が“自分のもの”になる
🧠 ポイント:専門用語にとらわれず、「言いかえる力」で理解が定着
→ 理解を“人に伝わる形”にできるようになる
🏡 家庭での遊び方(言い換えラリー):
👩「“かけ算”って、どういう意味だと思う?」
🧒「うーん……同じ数を何回もたす?」
👨「“わり算”は?」
🧒「何人かでわけるとき?」
👩「“ひき算”は?」
🧒「持ってたものが減るとき!」
📌 ワザ:
- 日常の中で思いついたらすぐにできる「ながら遊び」
- 逆に「“同じ大きさのグループを作る”って何算?」のように逆アプローチもOK
- 答えはひとつじゃない。複数の言い方を受け入れることで語彙と構造理解が深まる
💥 NG対応例:「正解が出てればいい」「説明は不要」
| ❌ 大人の意図 | 🧒 子どもの反応 | 🙅♂️ 具体的なNGシーン |
|---|---|---|
| テストスコア重視 | 「言葉にする意味がない」→応用でつまずく | 👨「とにかく正解出して。説明は飛ばしていいよ」 |
| 効率を上げたい | 「考えを外に出す習慣が育たない」 | 👩「言わなくていい、丸つけしておくね」 |
| 自信をつけさせたい | 「言葉に詰まる=できてない」と感じてしまう | 👨「何も言えないの?じゃあ、分かってないね」 |
🧭 改善のヒント:
- 答えではなく「どこから考えた?」にフォーカスを
- 説明の“正確さ”より“伝えようとする姿勢”をほめる
- 間違った言い換えもOK:「それ面白い!じゃあ別の言い方もあるかな?」
✨まとめ:「説明が苦手な子」は、“分かってない”のではなく、“言葉にする経験”が圧倒的に足りないだけ

「説明が苦手な子」は、“分かってない”わけではなく、“言葉にする練習”をしていないだけ
✅ 数学は「考えたことを言う力」も学力のひとつ
✅ 言葉にした瞬間に、“思考の解像度”が一段上がる
✅ 家庭での問いかけと対話が、算数を「伝えられる知」へと育てる