― 図形が見えないのではなく、“触れてない”のかもしれない
🧠 本記事が基づく教育法と要素
| 教育法 | 活用された視点・キーワード |
| 🌱 モンテッソーリ教育 | 空間把握の具体物/触覚・視覚の統合 |
| 🌀 シュタイナー教育 | 形の動き・リズムで捉える図形感覚 |
| 🧠 ブレイン・ベースド・ラーニング | 空間認知の脳回路は身体経験で育つ |
| 📖 コンストラクティヴィズム | 図形概念の「構成→再構成」経験 |
🧩 こんな症状ありませんか?
- 展開図や回転の問題になるとパニックになる
- 「どれが正しい形か選べ」と言われると全部同じに見える
- 面積や体積になると、急に自信がなくなる
→これは図形が“理解できない”のではなく、脳がまだ図形を扱う準備が整っていないだけかもしれません。
🌱 モンテッソーリの視点:
手で触れた図形、並べた図形、動かした図形は、脳の中で“操作できるイメージ”になる
- 実際に折る・切る・回す・重ねることで、頭の中に空間操作の「型」ができる
🌀 シュタイナー教育の視点:
図形は「形の動き」「リズム」「美的感覚」とともに捉えると、理解が自然に深まる
- ただ覚えるのではなく、「回転」「広がり」「つながり」を体感する経験が大切
🧠 ブレイン・ベースドの視点:
空間把握力は、“目”と“手”と“身体”の共同作業
- 机上の図だけでなく、身体を動かして空間を経験することで育つ
- 回転・折りたたみ・組み立ての感覚が、図形の理解に直結する
✅ 家庭でできる!「図形に強くなる感覚刺激」3ステップ
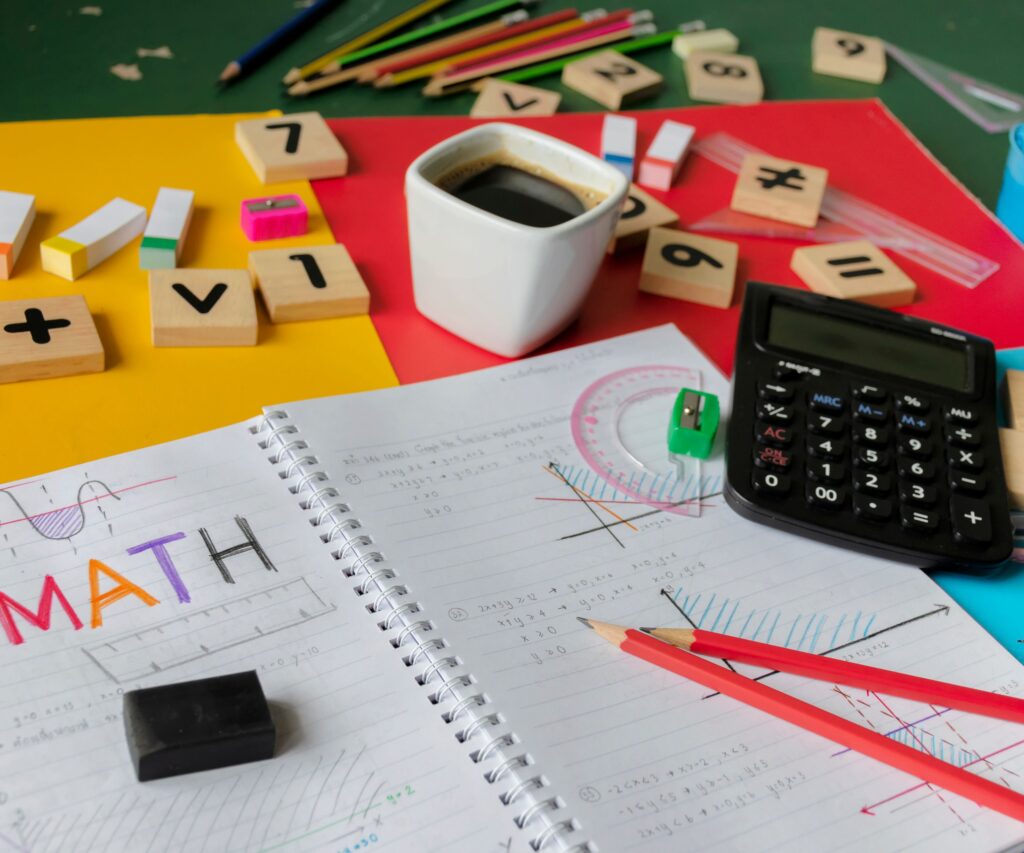
①【折り紙を“展開図”として遊ぶ】
📌 モンテッソーリ×身体経験:手で折って、開いて、形の“動き”を体感しよう
🧠 ポイント:図形の回転・展開・構成は、触って動かして初めて“自分ごと”になる
→ 頭の中で回せない子も、“手で動かせる”経験が増えると、少しずつイメージが育つ
🏡 家庭でのやり方例:
📘 ステップ1:折る前に「この正方形が、どうなると思う?」
📘 ステップ2:一緒に風船折りや箱折りなど、立体につながる形を作る
📘 ステップ3:「できたね!じゃあ開いてみよう。どんな線がついてる?」
👩「あれ?真ん中だけ四角になってるね」
🧒「こことここが三角になってるー!」
👨「これって、最初の形のどこだったんだろうね?」
📌 ワザ:
- 折り紙に「切り込み」を入れて組み立て→展開すると、展開図と立体がリンクしやすくなる
- 色つき折り紙や透明折り紙を使うと、“構造の見え方”がより明確に
②【LEGOやブロックを“体積”に変換】
📌 ブレイン・ベースド×構成体験:「組む・増やす・崩す」で、空間のイメージを育てる
🧠 ポイント:「空間を想像する力」は、実際に空間を“操作する経験”の積み重ねから育つ
→ 頭の中だけで考えるのが難しい子こそ、手でブロックを動かしながら学ぶと◎
🏡 家庭での遊び方例:
🧊 例1:「この形、3段積んだら何個分になる?」(縦のイメージ)
🧊 例2:「1列足すと、全部で何個になるかな?」(横のイメージ)
🧊 例3:「この形、箱に入る?入らない?」(容積感覚)
👨「この形を2個つなげたら、どんなのになると思う?」
👩「先に頭の中で想像してから、作ってみようか」
🧒「あ!思ったより大きかった!」
📌 ワザ:
- 透明のプラスチック容器や計量カップと組み合わせて「どの形がたくさん入る?」実験
- 一度作った形をスケッチする→崩す→再現チャレンジも、空間記憶を刺激する遊びに!
③【“図形を描く”ではなく“図形を構成”する遊び】
📌 コンストラクティヴィズム的な構築学習:「形を作る→壊す→別の形に再構成」が学びを深める
🧠 ポイント:「図形とは何か?」は、作り直す中で“気づくもの”
→ 描いて覚えるのではなく、“手で構成する”ことで意味をつかむ
🏡 家庭での遊び方例:
🔺 例1:「この三角形3つで、正方形ってできる?」
🔶 例2:「この形から、別の形つくってみよっか」
🟩 例3:「同じピースなのに、どうして別の形になったんだろう?」
👩「これ、前に作った台形とはどう違う?」
👨「あ、この形、ひっくり返すと別の形に見えるね!」
🧒「え、同じピースなのに、ぜんぜんちがう!」
📌 ワザ:
- 【七巧板(タングラム)】【マグネットパズル】【図形ブロック】など、パーツの少ないシンプルな教材が効果的
- 子どものつくった図形に名前をつけてもらう:「この形、何に見える?」→図形に感情や物語をつけて親しめる
💥 NG対応例:「これは覚えればいい」「見ればわかるでしょ?」
| ❌ 大人の意図 | 🧒 子どもの反応 | 🙅♂️ 具体的なNGシーン |
|---|---|---|
| 覚えて処理する力をつけたい | 「ピンとこない…」「丸暗記で乗り切るしかない」 | 👨「この展開図、4つあるけど正解どれ?」→🧒(全部同じに見える…) |
| 手数を減らしたい | 「図形は苦手」と思い込むきっかけに | 👩「見たらわかるでしょ?」→🧒(なんで分からないのかな、私だけ?) |
🧭 改善のヒント:
- 図形は“記号”として覚える前に、“身体で触れる”ことから始めよう
- 「作る・壊す・また作る」過程を一緒に楽しむことで、空間感覚はぐんと伸びる
- 回転・反転・構成などの“変化”を手で操作できるツールが、何よりの学び道具
✨まとめ:「図形が苦手な子」は、“見えない”のではなく、“動かしてない”だけかもしれない
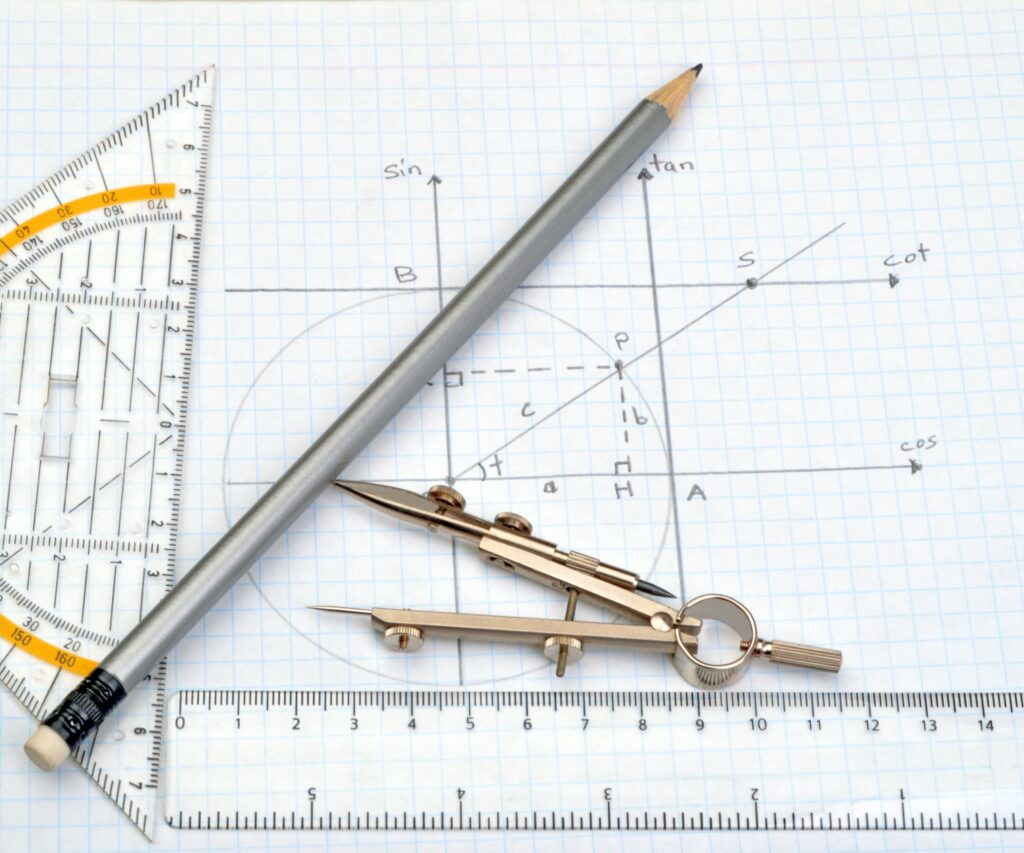
「図形が苦手な子」は、“見る力がない”のではなく、“動かす体験が足りない”だけかもしれない。
✅ 「触れる・動かす・再構成する」経験こそが、図形の本質的な理解を育てる
✅ 図形は“記憶”ではなく“経験”で学ぶもの
✅ 家庭でも“目・手・身体”を使った図形体験を意識的に増やそう!

